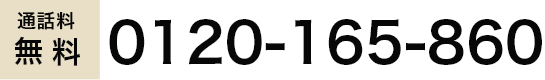資産の把握

お金の終活の第一歩として、自分の資産を把握することから始めましょう。リスト化すると整理しやすいので、下記のリストを参考にして自分の資産をセルフチェックしましょう。資産がチェックできたら、不要な契約は整理してきましょう。使っていないクレジットカードはありませんか。会員制サービスは本当に必要ですか。放置している不動産なども現金化しておくと、相続などの際に遺族が助かります。
資産のセルフチェック表
プラスの資産
預貯金
ネット口座も忘れずにリストアップ
有価証券
株式・債券・投資信託など。ネット口座もお忘れなく
現金
タンス預金の場所も記載
生命保険証券
契約内容まで確認
貸金庫
所在地を明記
貴金属や骨董品など
すべてもれなくリストアップ
不動産
自宅、相続した空き家など
マイナスの資産
借入金
保証人になっているものも記載
利用しているローン
住宅ローンや自動車ローンなど
加入しているもの
クレジットカード
契約しているものすべてリスト化
通信契約など
家のネット契約先、携帯電話契約先など
会員制サービス
サブスクリプションも忘れずに明記
必要なお金を計算

これから必要になるお金はどのくらいなのか、一度しっかり考えておきましょう。毎月の生活に必要なお金、生活以外のことで使うお金、医療費や介護費にあてるお金、この3つがわかれば、老後の生活を計画することができます。
毎月の生活に必要なお金
毎月の生活費が年金などの収入でプラスになるなら問題ありません。もしマイナスになる場合は、資産から補填する必要があります。平均寿命に数年の余裕を見て、この先に必要となる生活費への補填金額を計算しておきましょう。
生活以外のことで使うお金
趣味に使うお金、家のメンテナンス費、自身の葬儀代など、生活費以外で必要となるお金を洗い出しておきましょう。
医療費や介護費にあてるお金
それぞれの考え方で金額が変わります。将来、高齢者向け住宅の利用などを考えている場合は、入居一時金や毎月の利用料を確認しておきましょう。
今後の対策

プラスの資産と、マイナスの資産および今後必要になるお金を比べてみましょう。十分に足りているなら、残った資産が家族に残す遺産ということになります。もし、足りないようであれば早めに対策しましょう。
保険等の契約の見直し
高額な保険や通信契約、不必要な会員サービスなどは、すべて見直しましょう。
生活スタイルの見直し
自分の生活スタイルを見直して、できるだけ支出を抑えましょう。
資産の現金化
不動産の現金化、骨董品や貴金属の現金化を進めましょう。自宅を売却して、マンション等に暮らすことも選択肢に入ります。
遺産相続

生前に残したお金や不動産は、配偶者や子どもなどが相続することになります。遺産相続について考えておくことは、終活における重要事項です。遺産相続のことを何も考えずに亡くなってしまうと、家族や親族の中でトラブルが起こるかもしれません。3つのポイントを押さえて、遺族が困らない遺産相続の準備をしましょう。
遺言書を用意しておく
遺産相続のトラブルを防ぐための解決策のひとつが遺言書です。遺⾔書は法的効⼒を持つ書類です。元気なうちに、自分の考えを遺言書として残しておきましょう。
遺言書の種類
自筆証書遺言
全文を自筆で書いた遺言書です。紙とペンと印鑑があれば作成することができます。ただし、誤字や脱字、あいまいな内容などがあると効力を発揮できない場合があるので注意が必要です。
公正証書遺言
公証役場で作成する遺⾔書のことです。公証人と遺言者とは別に、2人以上の証人の同席が必要となります。公証人が遺言書を作成するため、無効になる恐れがありません。
秘密証書遺言
手書きや印刷で記した遺言書に封をしたのち、公証役場へ持参して遺言書として確認してもらうもの。公証人と遺言者とは別に、2人以上の証人の同席が必要となります。また、公証人に内容を知られません。
専門家の力を借りる
遺産の分け方に不安がある、相続させたい身内がいない、財産が多岐に渡るなど、遺産相続に悩みがある場合は、専門家の力を借りるのがおすすめです。法律に関わることなら弁護士、登記に関わることなら司法書士、相続税に関することなら税理士など、専門分野がありますので、相談内容にあわせた専門家を選びましょう。ただし、各専門家の中でも、さらに得意分野が分かれていることに留意してください。相続を得意とする専門家に相談しましょう。
相続税の節税対策をしておく
遺産を相続すると相続税が課税されます。ただし、相続税には基礎控除額として「3000万円+600万円×法定相続⼈の数」があり、これに収まる場合は申告や納税は不要です。基礎控除額を上回る場合は、取得金額に応じて相続人ごとに相続税の申告および納税が必要になります。取得金額が大きくなるほど税率が高くなりますので、相続人になるべく負担をかけたくない場合は、相続税の節税対策を行いましょう。
相続税の3つの節税対策
生前贈与
手間のかからない節税対策として、一般的に行われているのが生前贈与です。生前贈与には「贈与税」が課されますが、年間110万円以内であれば非課税で贈与できます。
不動産の購入
不動産を相続した場合、不動産の評価額は時価(市場価格)よりも低く算定されるため、現金の相続と比較すると相続税を抑えられます。
生命保険への加入
亡くなった方(被相続人)の死亡をきっかけとして受け取る財産のことを「みなし相続財産」といいます。生命保険の死亡保険金などは、みなし相続財産です。みなし相続財産は「500万円×法定相続人の数」が非課税となりますので、生命保険を相続税の節税に用いることができます。